みなさんこんにちは。
本日は、ガラパゴスフィンチの生態についてまとめていきたいと思います。
その名の通り、かの有名な南米エクアドル領ガラパゴス諸島に生息する鳥類、それがガラパゴスフィンチです。
この鳥は短期間の間に劇的な進化を遂げ、ダーウィンの進化論に少なからず影響を与えた鳥類なんです。
今回は、ガラパゴスフィンチについてのポイント、
以上7個の点についてお伝えします。
それでは、ガラパゴスフィンチの写真(画像)を見ていきましょう!
目次
ガラパゴスフィンチの画像(写真)!くちばしの特徴は?和名や学名はなに?


画像左がオス、右がメスとなります。
ガラパゴスフィンチは「スズメ目フウキンチョウ科ガラパゴスフィンチ属」に分類される、ガラパゴス諸島の完全固有種です。
ガラパゴスフィンチ属は通称「ダーウィンフィンチ」と呼ばれ、多くの種に分かれますが、外見からはほとんど見分けがつきません。
その全長と身体に対するクチバシの比率が唯一、見分けるポイントとなります。
ガラパゴスフィンチが世界中の進化論者から注目されたのは今からちょうど44年前、ガラパゴス諸島を強烈な干ばつが襲った時です。
それまでは柔らかい木々の種子を主食としていたガラパゴスフィンチですが、これらの木々は全て枯れ果ててしまったのです。
通常この様なことが起これば「絶滅」の2文字が頭をよぎりますが、このガラパゴスフィンチはより頑丈な硬い種子を食べる事を選択しました。
不思議なことに2〜3世代と極めて短いサイクルの間で、ガラパゴスフィンチのクチバシは新しい餌に適合し、10%以上のサイズアップという劇的な変化を見せたのです。
これはいったいどういう事なのでしょうか?
近年の研究では頭蓋や口吻(クチバシ)など、頭部の形成に欠かせない遺伝子が強く関与することが明らかになっています。
本来なら、この遺伝子のエラーは人間の場合は「口唇口蓋裂」などの発育不全を引き起こします。
しかし当のガラパゴスフィンチの遺伝子は、そのエラー因子とは僅かに違う特徴があり、それをうまく利用し短い世代サイクルで「太く大きく硬いクチバシ」を形成していたのです。
ダーウィン自身がフィンチと名付けた様にその容姿はありふれた鳥ですが、急激な環境の変化に子供・孫が迅速に進化し適応する、極めて例外的な鳥だったのです。
遺伝学のモデルケースとして、その適応力に各国の学者が血眼になり、研究を進めています。
専門用語では「異所的分化」と呼ばれています。
ちなみに表題の和名は「ガラパゴスフィンチ」そのものであり、学名は「Geospiza fortis」と呼ばれ、英名は「Medium Ground Finch」と呼ばれています。
次に、ガラパゴスフィンチの生息地(分布)はどこなのかについてお伝えします。
ガラパゴスフィンチの生息地(分布)はどこなの?どの季節で見ることができる?
ガラパゴスフィンチの生息地はガラパゴス諸島に限定されます。
もう少し正確にいうと、ガラパゴス諸島でもダーウィン島・ウォルフ島・エスパニョラ島・ヘノベサ島には分布していません。
南米諸島ということもあり、かなり乾燥した熱帯・亜熱帯の森林地帯に生息します。
次は、ガラパゴスフィンチの寿命はどれぐらいなのかについてお伝えします。
ガラパゴスフィンチの寿命はどれぐらい?繁殖期はいつなの?
ガラパゴスフィンチの寿命は平均4〜5年と言われています。
ガラパゴス諸島の生き物は国単位で厳重な保護下に置かれているので、飼育下寿命というものは存在しないと言っても過言ではないでしょう。
その繁殖期は雨季の直後となります。
ただ熱帯・亜熱帯のガラパゴス諸島では雨季自体が不定期であり、そういった点でも限られた環境に見事に適応してると言えるでしょう。
それでは次に、ガラパゴスフィンチの雛(幼鳥)の特徴をお伝えします!
ガラパゴスフィンチの雛(幼鳥)の特徴は?最大でどれくらいの体長に成長するの?
ガラパゴスフィンチは雨季直後に産卵・抱卵し、その卵は概ね2週間ほどで孵化します。
ヒナは当初、産毛に包まれており茶褐色の羽毛が生えますが、その後換羽を経てオス・メスそれぞれの体色へと変化します。
ヒナ自体はごく一般の綿毛に包まれた形状をしていますが、困ったことに近縁種と交雑しやすいという親側の事情がここ「ガラパゴス」ではよく起こり得るのです。
ダーウィンフィンチの仲間はクチバシの形状と全長以外ほぼ近縁であり、過去の進化過程でも同様の事が起こっていたのではないでしょうか?
ガラパゴスフィンチ純粋種は英名でMediumとあるように、そこまで大柄にはならず14~15cm程の全長で成鳥になります。
次に、ガラパゴスフィンチの鳴き声(さえずり)の特徴についてお伝えします。
ガラパゴスフィンチの鳴き声(さえずり)の特徴は?
ガラパゴスフィンチはそのクチバシの進化に目が行きがちですが、鳴き声にもある種の特徴があります。
短期間の進化でクチバシが肥大化しましたが、それは直接に鳴き声には作用していません。
普段はごく普通の小鳥のようなさえずりを行うのですが、こと群れ内に他種の侵入者が入ってきたときは「警戒音」のような鳴き声を発することが知られています。
ですが多種との交雑も進化の過程で頻繁に行っているので、この鳴き声は「警戒」ではなく「試し音」という学者もいるほど難解なものと捉えられています。
それでは、ガラパゴスフィンチは何を餌(食べ物)にしているのかについてお伝えします。
ガラパゴスフィンチは何を餌(食べ物)にしているの?吸血するの?

写真は吸血行為を行う「ハシボソガラパゴスフィンチ」です。
ガラパゴスフィンチは誤解されがちですが、吸血行為は一切行いません。
彼らは種子を中心とした「雑食性」であり、ガラバゴス諸島内の限られた餌を摂取するために、くちばしの形状を目まぐるしく短期間で進化させただけです。
その他にガラパゴスゾウガメ・イグアナなどの寄生虫をついばむ、クリーニングバードの一面も持ちます。
吸血行為を行うのは「ハシボソガラパゴスフィンチ」ただ一種です。
この種が吸血行為を行うきっかけになったのは「カツオドリ」の寄生虫をついばんでいるうちに、その皮膚を傷つけてしまったことに起因しています。
吸血というと印象が悪いのですが、血液自体はかなり栄養価が高く資源に乏しいガラパゴス諸島内ではうってつけの栄養補給減だったのです。
当のカツオドリを心配するでしょうが、体長差から人間が蚊に刺されたようなもので、吸血されている側は驚くことにほぼ無関心なんです。
この様に食性そのものを短期間、そして少しのきっかけで極端に変えてしまう点でも、進化の過程を解き明かす行為として非常に注目されているのです。
最後に、ガラパゴスフィンチの性別雌雄(メスオス)の見分け方をお伝えします!
ガラパゴスフィンチの性別雌雄(メスオス)の見分け方は?
ガラパゴスフィンチの雌雄判別は外見上で可能になります。
オスは全身黒一色ですが、メスの羽毛は茶褐色味が入ります。
メスの方が少しだけ体長も大きく、この2点で判別が可能となるでしょう。
それでは、今回お伝えしたことをまとめていきましょう!
ガラパゴスフィンチのまとめ!
いかがでしたでしょうか?今回お伝えした重要なポイントは7個ありました。
覚えているでしょうか?1個ずつ振り返っていきましょう!
①ガラパゴスフィンチの画像(写真)!くちばしの特徴は?和名や学名はなに?
ガラパゴスフィンチのクチバシはその食糧難から太く大きく短期間で変化しました。
和名・学名はそれぞれ「ガラパゴスフィンチ」「Geospiza fortis」となります。
②ガラパゴスフィンチの生息地(分布)はどこなの?どの季節で見ることができる?
ガラパゴス諸島の完全固有種であり、1年を通し見れる留鳥となります。
③ガラパゴスフィンチの寿命はどれぐらい?繁殖期はいつなの?
平均寿命は4~5年ほどと言われています。
④ガラパゴスフィンチの雛(幼鳥)の特徴は?最大でどれくらいの体長に成長するの?
ヒナは初期は茶褐色ですが巣立ち換羽期を迎えるとそれぞれオス・メスの羽色に変化します。
平均体長は14~15cmになります。
⑤ガラパゴスフィンチの鳴き声(さえずり)の特徴は?
通常は他の小型種同様ですが、群れ内に他種が侵入すると「警戒」「試し音」をさえずります。
⑥ガラパゴスフィンチは何を餌(食べ物)にしているの?吸血するの?
吸血をするのは「ハシボソガラパゴスフィンチ」のみです。
主食は木々の種子を中心に、他の動物の寄生虫なども栄養源とします。
⑦ガラパゴスフィンチの性別雌雄(メスオス)の見分け方は?
オスは黒一色、メスは茶褐色が入る体色となります。
それでは今回はこれで失礼します。
最後までご覧いただきありがとうございました。
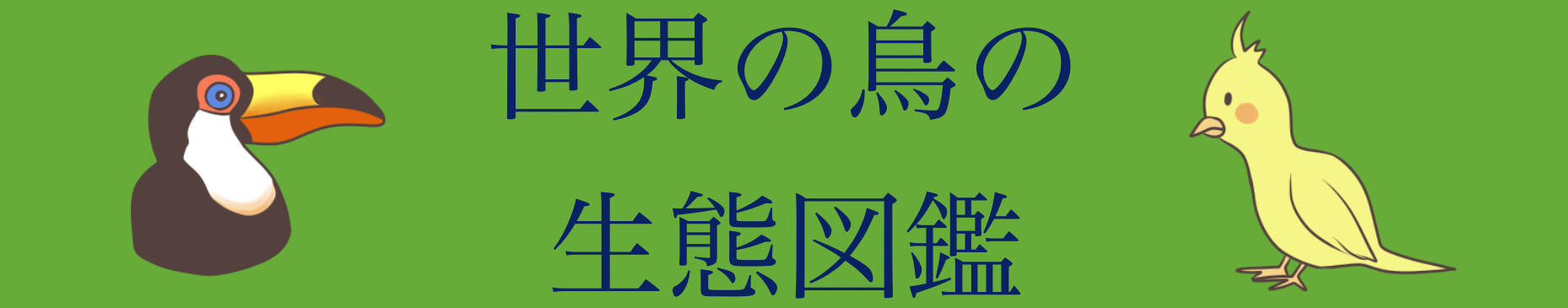




コメントを残す